赤ちゃんのお世話に慣れてきたと思ったら、あっという間に幼児期へ。
「もう赤ちゃんじゃないんだ」と気づく瞬間は親として嬉しい反面、少し寂しくもあります。
赤ちゃん期と幼児期では、食事・睡眠・遊び・親の関わり方など、育児スタイルが大きく変わります。
この記事では、父親目線で感じた赤ちゃん期から幼児期への育児の変化を、実体験を交えてお伝えします。
「これから幼児期を迎えるパパママ」にとって参考になるよう、実体験を交えてご紹介します。
Contents
赤ちゃん期と幼児期、何が違う?

育児スタイルの根本的な変化
赤ちゃん期(0歳ごろ)
- 授乳、オムツ替え、寝かしつけが中心
- 親が主導する「お世話育児」
幼児期(1〜3歳ごろ)
- 「自分でやりたい!」という自己主張が増加
- 親子で「一緒に生活を作る」段階へ
私自身、娘が1歳を超えたあたりから、この変化を強く感じました。
印象的だったエピソード
娘が自分で靴を履こうと奮闘する姿を見たときに、「手伝わなきゃ」と思う一方で、うまくいかずに「できない」と泣き出す娘に、「待ってあげる忍耐力も必要だな」と実感しました。
食事面の変化
ミルクから離乳食、そして幼児食へ
赤ちゃん期
- ミルクや母乳が中心
- 「飲めばOK」というシンプルさ
幼児期
- 食べる量や好き嫌いがはっきり
- 「遊びながら食べる」「気分で食べない」との戦い
父親目線で大変だったこと
ある日、せっかく作ったおかずを一口も食べず、スプーンを投げられたときは思わずため息…。
でも翌日には「これ食べたい!」と自分から手を伸ばしてくれる。
このギャップこそが育児の楽しさであり、難しさだと感じています。
離乳食作りの思い出
我が家は夫婦ともにシフト制。休みが重なることがほとんどなく、仕事後の深夜に2時間かけて1週間分の離乳食を作っていました。
正直、疲労困憊でした。
でも、娘がおいしそうに食べる姿を見た瞬間、すべての疲れが吹き飛びました。
外食やお出かけでの工夫
持ち物の変化
- 赤ちゃん期:哺乳瓶、粉ミルク
- 幼児期:おやつ、幼児食、水筒など種類が増加
一方で、同じものを親子で食べられる喜びも増えてきます。
先日、公園でサンドイッチを一緒に食べながら、「サンドイッチ、一緒に食べたい?」と聞いたら、「うん!」と元気に答えてくれた瞬間には、育児の新しい楽しさを感じました。
睡眠リズムの変化
夜泣きからの解放
赤ちゃん期の悩み
- 頻繁な夜泣き
- 何度も夜中に抱っこで部屋を歩き回る
幼児期の変化
- 夜泣きが減り、まとまって眠れる
- 久しぶりに「連続4時間睡眠」の喜びを実感
この時間を趣味や仕事に使えるようになったのは、親にとって本当に大きな変化でした。
お昼寝の回数が減る
ただし、お昼寝が減ると昼間に自分の時間が取りにくくなるという新たな課題も。
日中は子どもと一緒に遊んだり付き合ったりする時間が増えます。
昼食後に「まだ遊ぶ!」と言われ、1時間遊ぶことになった日には、体力の消耗とともに親としての忍耐力も鍛えられました。
遊び方・コミュニケーションの変化

おもちゃ遊びから「一緒に遊ぶ」へ
赤ちゃん期
- 基本的なお世話が中心
幼児期(1歳前後〜)
- 言葉や手足の動きが発達
- 「遊び相手になれる喜び」を実感
先日、娘と一緒にブロックで遊んでいたら、夢中になりすぎて腰が痛くなるほどでした。
でも、笑顔で完成させた作品を見せてくれた瞬間の達成感は格別でした。
言葉が増えて会話が楽しい
幼児期の大きな変化が「言葉の爆発期」。
「パパ」「ママ」から始まり、二語文、三語文へと発達していく過程を間近で見るのは本当に感動的です。
「パパ、あっち行こう!」と誘われたときには、ただお世話するだけでなく、一緒に行動する楽しさを実感しました。
外の世界との関わり
公園デビューやおでかけ
赤ちゃん期
- 家やベビーカーでの移動が中心
幼児期
- 「自分で歩く!」と主張
- 公園で他の子と関わる機会が増える
娘が初めて友達と一緒に砂場で遊ぶ姿を見て、「社会性の芽生えを感じられるんだな」と感動しました。
幼稚園・保育園を意識し始める
我が家の場合、娘が生まれて半年ほどで「幼稚園・保育園はどうする?」という話題が出てきました。
赤ちゃん期とは違い、「教育」「集団生活」といった要素が育児に入ってくるのも幼児期ならではの変化です。
初めての面接や見学の際、妻が緊張した表情をした瞬間には、「サポートしてあげなきゃ」と家族として、父親としての責任感を強く感じました。
親の気持ち・ライフスタイルの変化
自分の時間の使い方
赤ちゃん期
- とにかく「睡眠不足」との戦い
幼児期
- 夜まとまって眠れるように
- 少しずつ自分の時間を持てる
私はその時間を趣味のゲームやブログ執筆に使っています。
ただ、昼間の遊び相手として体力を使うため、夜の自由時間は大切にしています。
「かわいい」から「向き合う」育児へ
赤ちゃん期
- 「とにかくかわいい」気持ちが勝つ
幼児期
- イヤイヤ期や自己主張に直面
- 試行錯誤と忍耐力が求められる
もちろん幼児期の子どももかわいいですが、親として成長を実感すると同時に、忍耐力も試されます。
先日、「これやらない!」と泣き叫ぶ娘に向き合い、根気強く説明して受け入れてもらえた瞬間、育児の楽しさとやりがいを改めて感じました。
パパへのワンポイントアドバイス
今まさに赤ちゃん期から幼児期への移行期で戸惑っているパパへ。
まず1日10分だけでも、子どもと一緒にじっくり遊ぶ時間を作ってください。
どんなに短くても、親子の関わりを意識するだけで、育児の方向性が見えてきます。
この10分で:
- 言葉の発達
- 遊び方の変化
- 子どもの気持ちの変化
に気づくことができます。
悩んだ時は「まずは触れ合う時間」を意識してみてください。
まとめ|赤ちゃん期と幼児期の違いを楽しもう
赤ちゃん期 = 「お世話中心」 幼児期 = 「一緒に生活を作る時期」
食事・睡眠・遊び・社会性など、子どもの成長に合わせて育児スタイルが大きく変わります。
父親目線で感じたこと
- 大変さの種類は変わる
- でもその分「一緒に楽しめる時間」が増える
赤ちゃん期の思い出を大切にしながら、幼児期の新しい発見を楽しんでいきましょう!
なお、子供2人の育児でミルク育児と母乳育児の違いを父親目線で考えてみたといった記事も書いていますので、こちらもあわせてご覧いただければ幸いです。

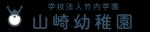


コメント